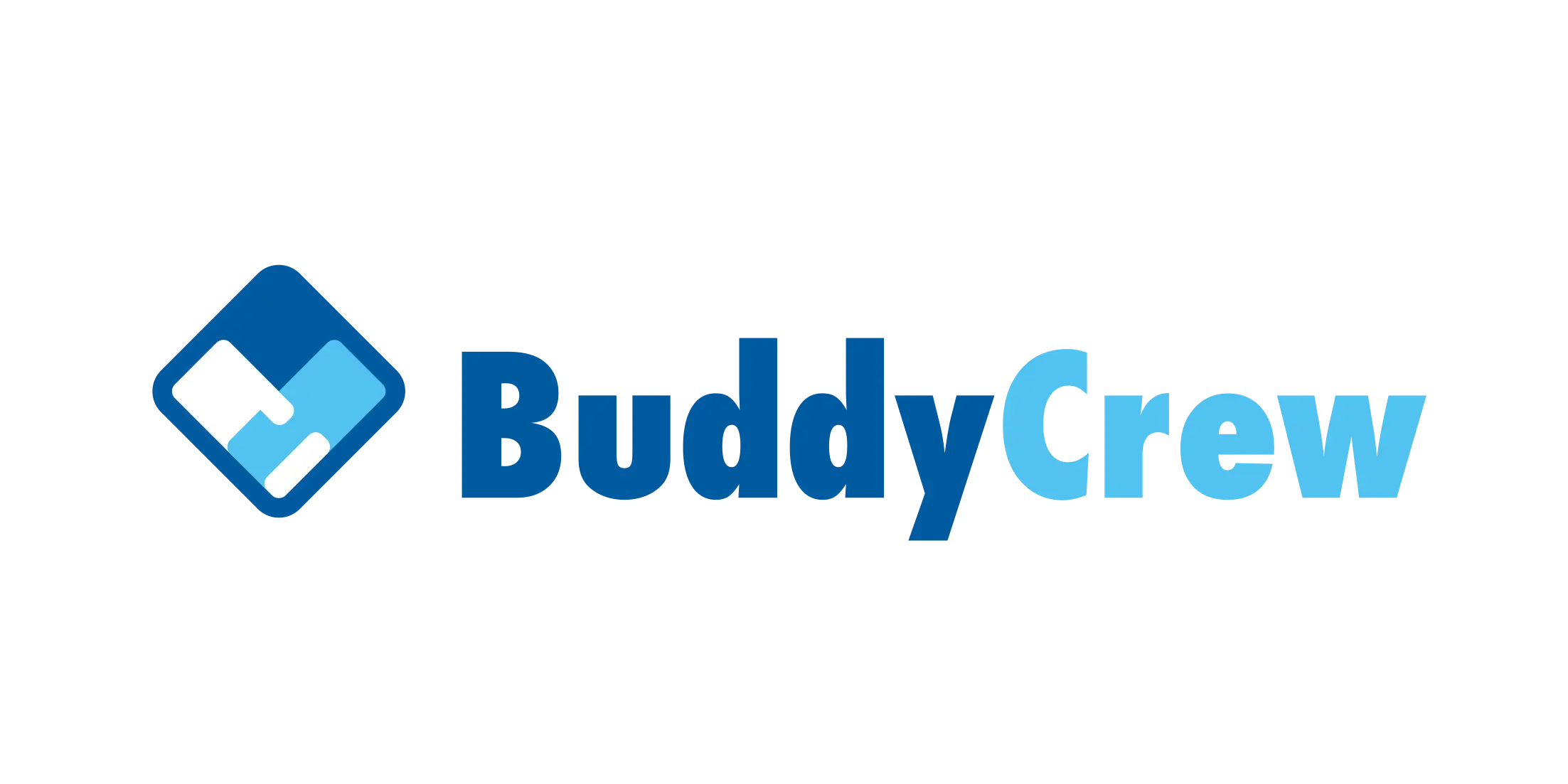介護現場で「ありがとう」が通じる瞬間

~言葉を越えて、心がつながる瞬間~
介護の現場では、日々の業務の中に、小さなドラマがたくさんあります。
特に外国人スタッフが関わる介護の現場では、「文化も言葉も違う中で、本当に心が通じるのだろうか?」という不安の声も少なくありません。
しかし、言葉を超えた“ありがとう”の瞬間は、たしかに存在します。
それは、ケアを受ける側と、提供する側が“人と人”として向き合ったときに生まれるものです。
■ 実際のエピソード:ミャンマー出身スタッフと、無口な利用者さん
ある介護施設に勤めるミャンマー出身のAさん。
日本に来て1年、特定技能で介護業務に従事しています。真面目でやさしい性格ながら、日本語はまだまだ勉強中。
Aさんが担当していたのは、寡黙でなかなか笑顔を見せない男性利用者Bさん。
介助の際も「はい」「いらない」と短く答えるだけで、なかなか心を開いてくれませんでした。
■ 少しずつ重ねた“言葉にならない”関わり
それでもAさんは、毎日Bさんの顔を見て、目を見て、ゆっくりと話しかけ続けました。
「おはようございます」
「今日は寒いですね」
「ご飯、全部食べましたね!すごいです!」
最初は無反応だったBさんも、ある日ふと、うなずいてくれた。
さらに数日後、歯みがきの介助を終えた後に、ぽつりとこう言ったのです。
「……ありがとう」
■ Aさんの目に涙が浮かんだ、その理由
「ありがとう」——その言葉自体は短いけれど、
外国人スタッフにとっては、それ以上の意味を持ちます。
Aさんは後にこう語ってくれました。
「Bさんが“ありがとう”と言ってくれたとき、自分の日本語が通じたことも嬉しかったけど、
“この仕事をやっていてよかった”と思えたんです。心がつながった気がしました。」
■ “伝わる”のは、言葉よりも“姿勢”
介護現場では、日本語が流暢でなくても、「やさしい声かけ」「丁寧な手の動き」「一緒に笑う表情」など、非言語のコミュニケーションが何よりの信頼を築いてくれます。
「ありがとう」は、相手が心から満たされたときに出てくる言葉。
それが通じた瞬間は、まさに介護の“本質”が現れる瞬間なのかもしれません。
まとめ:ありがとうの重みを、私たちは知っている
言葉に不安がある外国人スタッフでも、
介護の現場で「ありがとう」が通じるとき、
それは**“あなたの存在が受け入れられた”という最高のメッセージ**になります。
外国人材の受け入れは、ただ人手を増やすだけではありません。
現場に新しい視点と、あたたかいエピソードをもたらしてくれる存在でもあります。