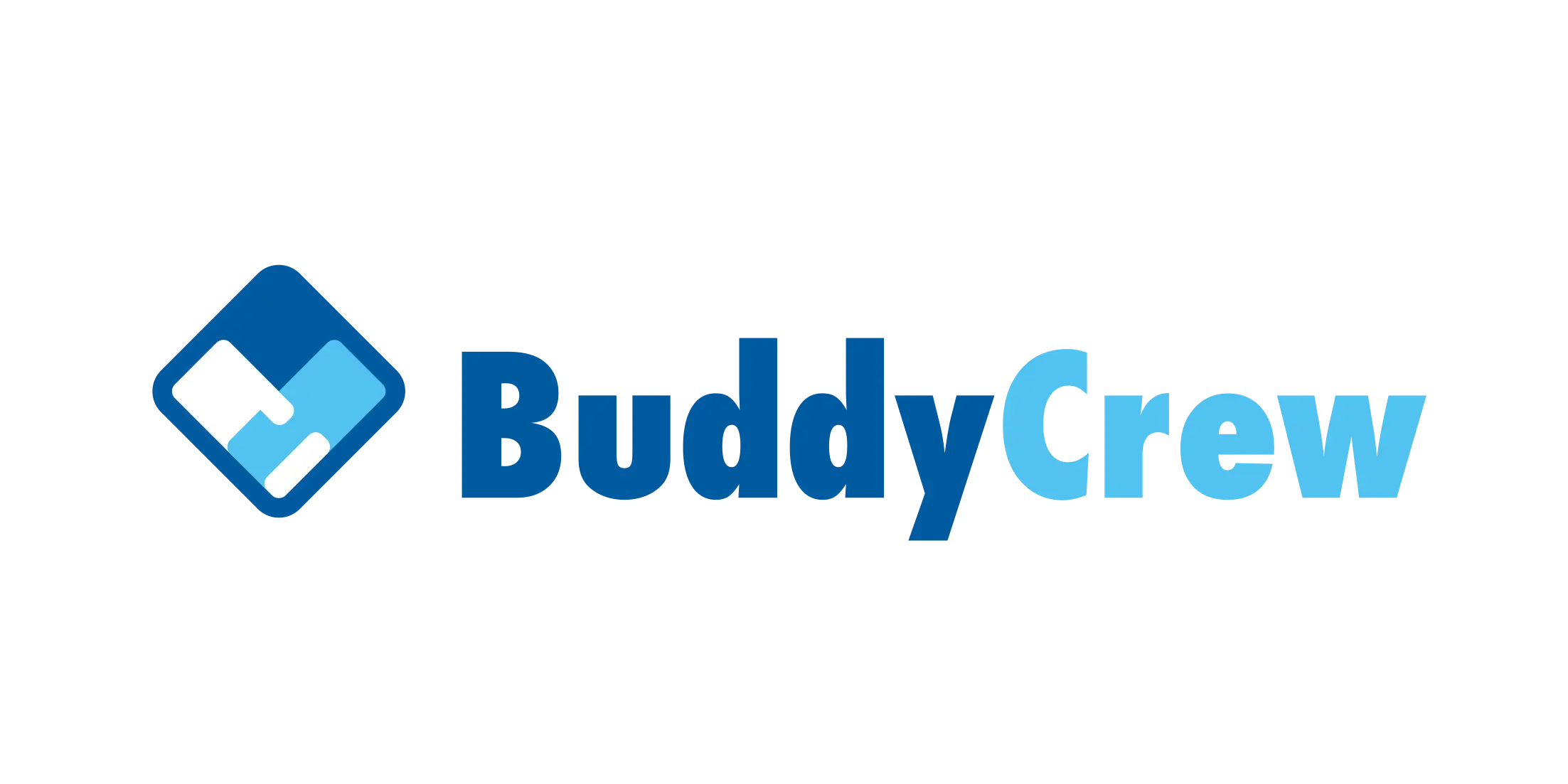先輩が語る!外国人材の教育で一番苦労したこと

~“伝えたつもり”が通じない、その壁をどう越えたか~
外国人材の受け入れが当たり前になりつつある今、教育係として現場に立つ日本人スタッフの役割はますます重要になっています。
でも、「どう教えたら伝わるのか分からない」「同じミスを繰り返されてしまう」「本人のやる気が見えないように感じる」など、現場の悩みは尽きません。
今回は、実際に外国人スタッフの教育に関わった**製造現場の先輩社員・Kさん(30代)**に、教育で一番苦労したことと、それをどう乗り越えたかを語っていただきました。
■ 苦労したのは「“わかった”が、本当に分かったかどうか分からない」こと
「最初にびっくりしたのは、こっちが説明して“OK?”って聞くと、必ず“はい”って言うんです。でも、実際に作業してもらうと全然違うことをしていたりして…。最初は正直、『ちゃんと聞いてないんじゃないか?』って思ったこともありました。」
Kさんが最初にぶつかったのは、“言語の壁”というよりも、「理解の確認ができない」ことだったといいます。
どれだけ説明しても、相手が本当に理解しているかを判断する方法が分からず、“伝えたつもり”が何度も裏切られる感覚にストレスを感じていたそうです。
■ 乗り越えたきっかけは「教える手段を変える」こと
「途中から、言葉で説明するのをやめて、『実際にやって見せてからやってもらう』スタイルに切り替えたんです。あと、作業手順を写真付きでマニュアルにしたら、明らかに理解度が変わりました。」
Kさんが取った工夫は以下のようなものでした:
- 説明のあとに復唱や実演をしてもらう
- 作業手順をイラスト+写真+番号付きでマニュアル化
- 「できたこと」に対して小さくてもすぐに褒める
- 同じ外国人の先輩スタッフにフォロー役を頼む
こうした変化によって、相手の表情が変わったのを実感したと言います。
「それまでは、たぶん“分かってないのに聞けない”状態だったんでしょうね。こっちが歩み寄ることで、相手の方からもどんどん質問が出てくるようになって、チーム全体の雰囲気もよくなりました。」
■ 教える側が「理解される責任」を持つこと
Kさんは、外国人スタッフの教育を経験したことで、“教える”ということの意味が変わったと語ります。
「最初は、“教えたのにできない”と思ってた。でも今は、“伝え方が伝わってないんだな”って思えるようになったんです。つまり、相手が理解できるように伝えるのが“教える”ってことなんですよね。」
そして、「この経験は、後輩の日本人社員にも同じように役立っている」とも。
まとめ:「伝わらない」は壁ではなく“きっかけ”になる
外国人材の教育で一番苦労するのは、「伝えたことが、伝わっていないとき」。
でも、それをどう乗り越えるかは、“伝える側の姿勢”にかかっています。
- わかりやすくする工夫(図解・実演・簡単な日本語)
- 相手が安心して質問できる空気づくり
- 理解できたことを一緒に喜ぶ姿勢
これらの積み重ねが、信頼と定着につながっていきます。
「教えることに慣れていない人でも、失敗を重ねながら一緒に成長していける。それが、外国人材と働く現場の醍醐味です」と語るKさんの言葉が、何よりの答えかもしれません。