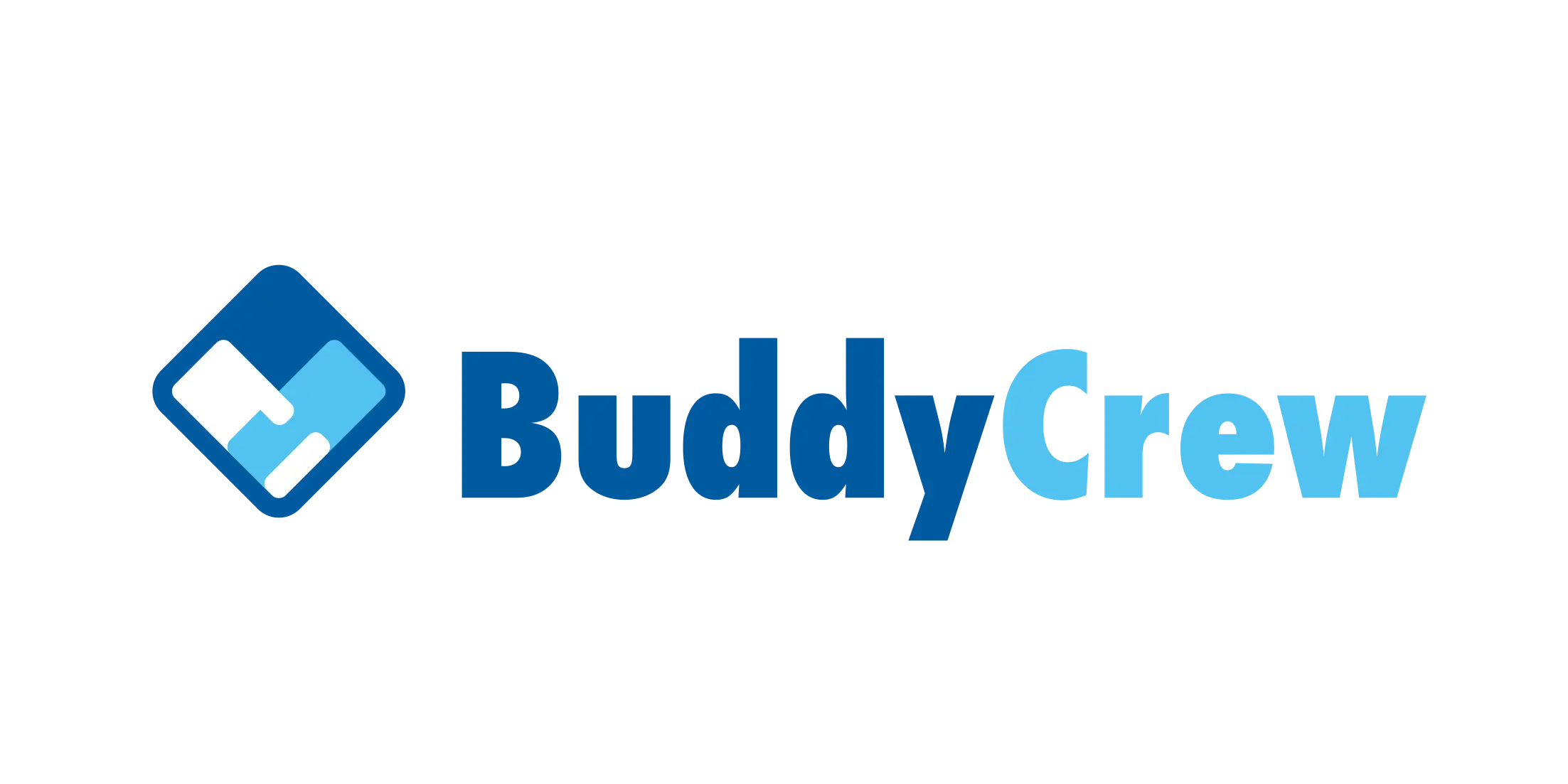建設現場の救世主?外国人材のリアルな実態

かつて「男の仕事」と言われた建設業。日本人の若者離れが進む一方で、現場を支えているのは、じつは増え続ける外国人労働者たちです。
彼らは本当に「救世主」なのか?それとも、制度のスキマを埋める“都合のいい労働力”にすぎないのか?
現場で働く外国人材のリアルな実態を、制度・現場・企業の視点から掘り下げてみましょう。
1. 建設業を支える外国人材の急増
建設業における外国人労働者数は年々増加しています。技能実習、特定技能、建設就労者(旧日建連ルート)など、複数の制度を通じて、外国人材が現場に入るケースが増えました。
特に人手不足が顕著な地方の現場や、大規模な再開発・インフラ工事の分野では、彼らなしでは工期が回らないという企業も少なくありません。
2. 実態①:言葉の壁より“作業の感覚”
日本語能力に課題がある…という声はよく聞かれますが、現場では「細かい指示を出さなくても動けるか」が大事とされています。
実際に、数か月で基本動作やチームワークを覚え、現場で重宝される外国人も多くいます。
🔧 現場の声:
「○○してって言わなくても動いてくれる。日本人の若い子より根気がある」(土木現場監督・40代)
ただし、安全管理が徹底される現場では、やはり言葉の壁は無視できません。特に重機・高所作業では通訳やピクトグラムによる補助が求められています。
3. 実態②:制度による違いと混乱
建設業で働く外国人は、主に以下の制度で在留しています。
| 制度 | 主な特徴 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 技能実習 | 育成目的、作業の幅が限定される | 最長5年 |
| 特定技能 | 試験合格者、即戦力前提 | 最長5年(更新不可) |
| 建設特定活動 | 建設特化、技能実習からの移行が可能 | 最長5年 |
制度の違いにより、同じ仕事でもできる作業・できない作業が異なる場合があり、企業側も「誰に何をさせられるか」が分かりにくいという問題があります。
4. 実態③:離職と転職のリスク
「すぐ辞める外国人が多い」と言われることもありますが、背景には待遇格差や生活支援の不足があることも多いです。
• 宿舎が古い・寒い
• 給料明細が不明瞭
• 母国に仕送りする必要がある
• 同国人との人間関係トラブル
これらの要因で不安定になり、やむを得ず転職するケースもあります。とくに特定技能では転職が制度上可能なため、「定着」のためには職場環境の整備が不可欠です。
5. 実態④:彼らの“誇り”とキャリア意識
忘れてはならないのが、外国人労働者の多くが「技術を身につけたい」「将来は母国で活かしたい」という思いを持っているという点です。
中には日本語検定や建設技能試験に挑戦し、将来的には「特定技能2号」や永住を目指す人もいます。
🔩 本人の声:
「最初は道具の名前もわからなかった。でも、今は鉄筋図面も読める。いつかベトナムで会社を作りたい」(特定技能・鉄筋職人/ベトナム出身)
6. まとめ:一緒に“現場をつくる”という視点へ
外国人材は単なる“労働力”ではなく、“仲間”として受け入れる視点がこれからは求められます。
建設業における彼らの存在は、決して一時しのぎのものではなく、日本のインフラを一緒に支えるパートナーです。
制度や言葉の壁は確かにありますが、それを超えて「共につくる現場」を目指すことで、企業にとっても本人にとっても大きな価値を生み出すことができるのです。
✍ 編集後記
現場で汗を流す彼らの表情は真剣そのもの。
それは日本人も外国人も関係なく、同じ「職人の顔」でした。