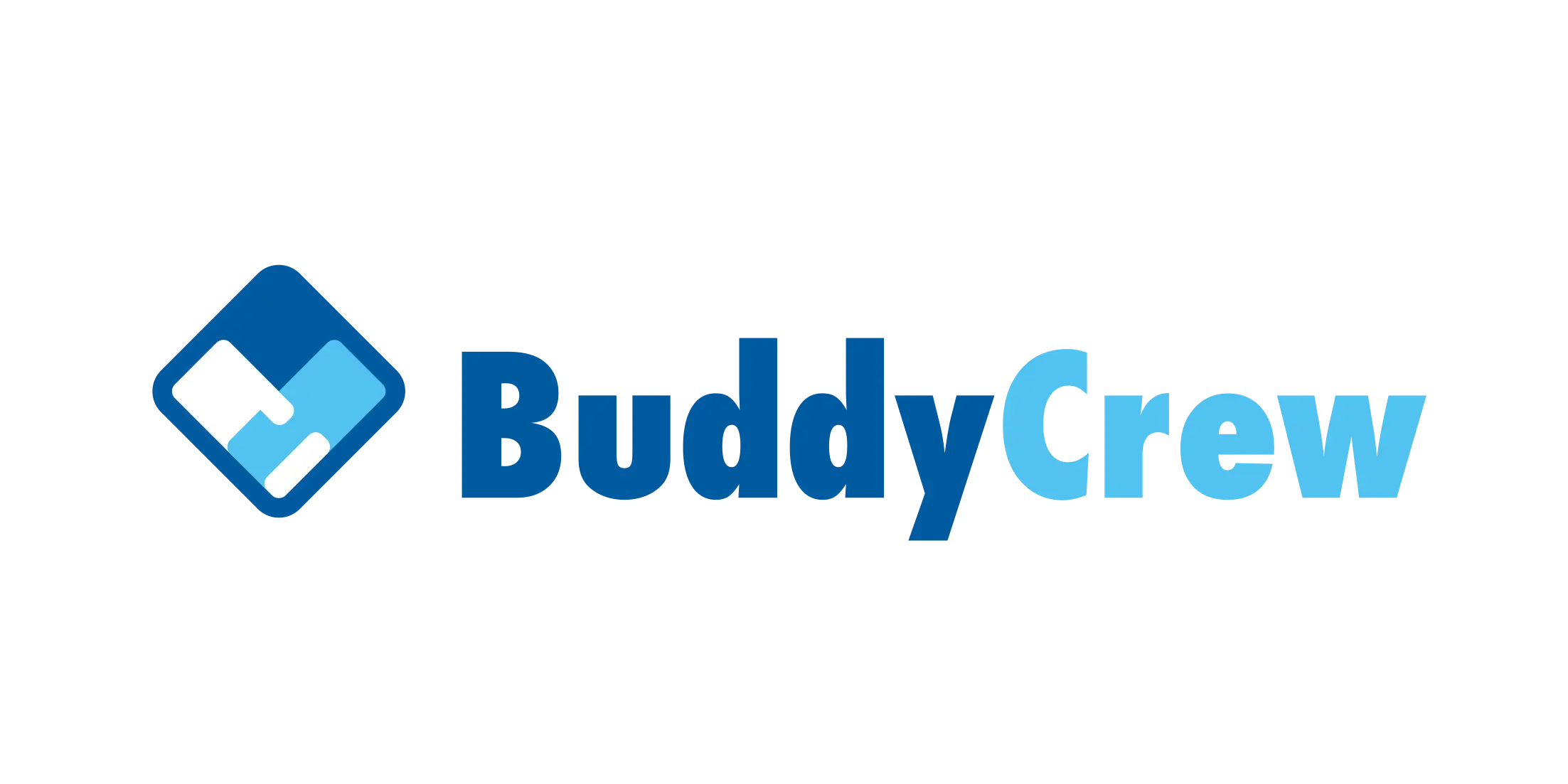特定技能vs技能実習!製造業に合うのはどっち?

近年、深刻な人手不足に悩む製造業。解決策として注目されているのが、外国人労働者の受け入れです。中でも「技能実習」と「特定技能」の2つの制度は、多くの企業が導入を検討しています。
でも、結局どちらの制度が製造業には向いているのでしょうか?
今回は、それぞれの制度の特徴と、現場でのリアルな使い勝手を比較しながら、製造業にとって本当に“使える”制度はどちらなのかを掘り下げていきます。
技能実習制度とは
技能実習は、もともと「開発途上国への技術移転」を目的に設計された制度です。日本の技術を学び、自国に持ち帰って役立てるという建前のもと、最大5年間の在留が可能です。
製造業では、プレス加工、鋳造、溶接などの職種で多く活用されています。
メリット:
• 受け入れ人数枠の柔軟性
• 企業が教育を前提として雇える
デメリット:
• 制度の目的が「人材育成」のため、長期的な戦力化が難しい
• 言葉や生活のフォローなど、企業負担が重い
• 実習計画や監理団体との連携が必須で手続きが煩雑
特定技能制度とは?
一方、特定技能は「即戦力となる外国人材」を受け入れる制度です。2019年に創設された比較的新しい制度で、製造業では「産業機械製造」「電気・電子情報関連産業」「素形材産業」などが対象職種に含まれています。
メリット:
• 即戦力としての採用が可能(試験に合格した人材)
• 最長5年まで在留でき、技能実習からの移行も可能
• 直接雇用が基本で、指導コストが抑えられる
デメリット:
• 人材確保が難しい地域も(試験合格者に限られる)
• 管理・支援体制の整備が必須(登録支援機関との連携)
• 日本語力は人によってばらつきがある
製造業に合うのはどっち?
結論から言えば、「中長期的な戦力」を求めるなら特定技能が有利です。
技能実習は、制度上どうしても“育成枠”としての制限があります。3年・5年で帰国することを前提にした運用のため、製造ラインでの戦力化が進んだ頃には退職…ということも珍しくありません。
一方、特定技能は“できる人”を前提に採用できるため、教育コストも少なく、即戦力になりやすい点が魅力。さらに、技能実習からの移行者も多く、すでに日本での生活に慣れた人材を採用できるケースも増えています。
もちろん、地域や職種、会社の体制によっては技能実習の方がマッチする場合もあります。たとえば、工場が地方にあり、言語や生活サポートに自信がある企業であれば、技能実習でも十分に定着を目指せるでしょう。
まとめ
• 技能実習:育成型、手厚い支援ができる企業に向いている
• 特定技能:即戦力型、戦力不足を早急に補いたい企業におすすめ
製造業の現場では、“教える余力があるか”“すぐに戦力がほしいか”が制度選びの大きな分かれ道。
制度のメリット・デメリットを正しく理解し、自社に合った形での外国人材活用を進めていきましょう。