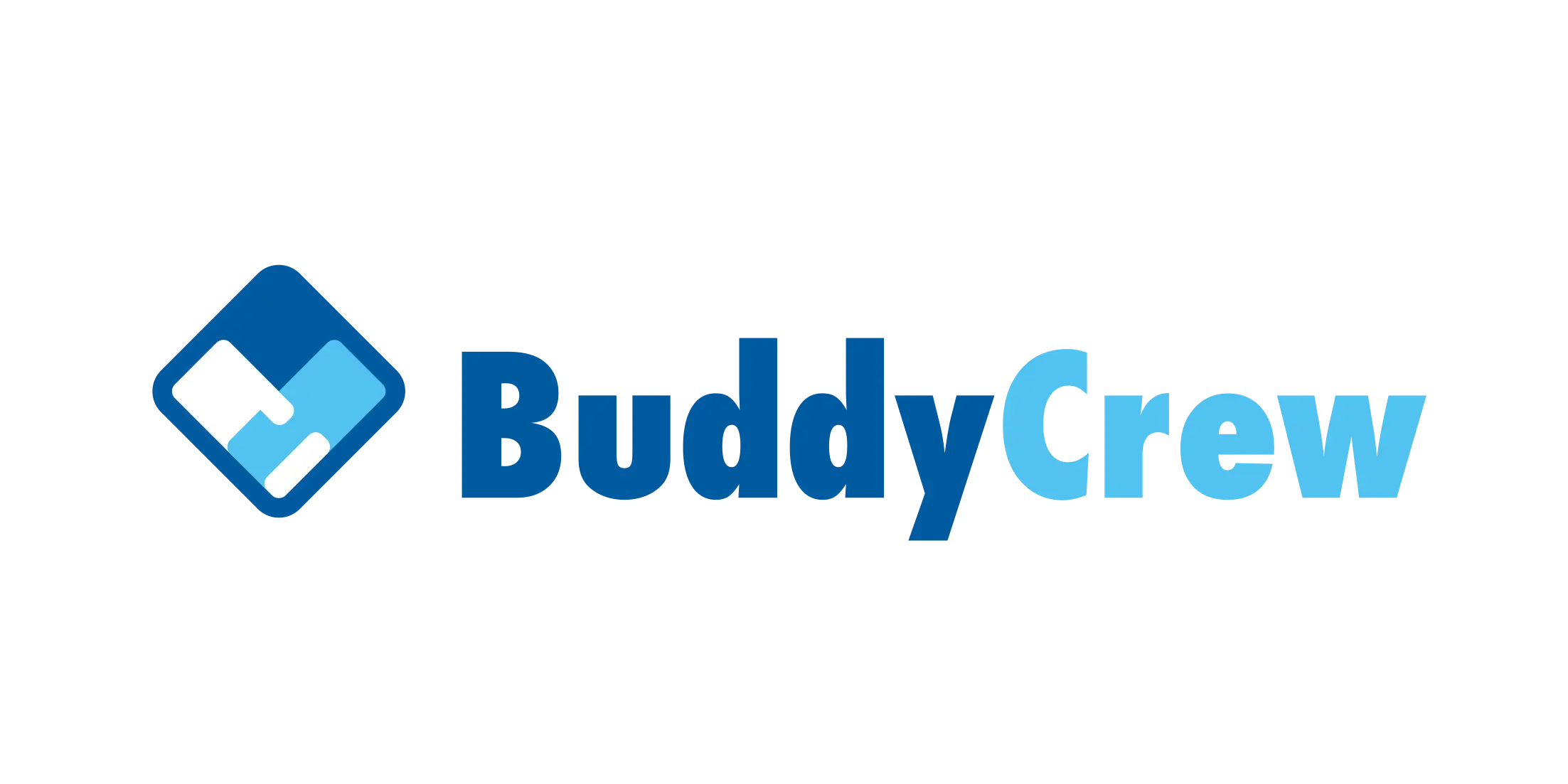電気積算のミスあるあるとその対策方法

~“うっかり”がトラブルに?精度アップのコツを解説!~
電気工事の見積りや発注精度を左右する「電気積算」。
数量や仕様を拾い間違えると、現場での材料不足やコストオーバーにつながる重大なミスになりかねません。
今回は、実務の中でよく見かける「電気積算のミスあるある」と、その防止・対策方法を、実践的にまとめました!
ミスあるある①:図面の見落とし・拾い漏れ
💬 よくあるケース
- 照明器具の一部が他ページに記載されていて拾い忘れ
- 予備回路や非常電源回路が別図面に隠れていた
- コンセントが凡例記号と違って見落とした
✅ 対策方法
- 「凡例(シンボルマーク)」は積算前に必ずチェック
- 図面を印刷してマーキング拾い or 積算ソフトで図面をなぞる
- 「器具リスト」と図面の突合せ確認をルール化
- 拾い終わったら「誰かにチェックしてもらう」ダブルチェック体制
ミスあるある②:単価の設定ミス・計上漏れ
💬 よくあるケース
- 電材の単価が古く、実勢価格とズレていた
- 配線やケーブル類の附属部品(支持金具、ジョイントなど)を忘れる
- 小型器具に手間を見込まず、実行予算が足りなくなる
✅ 対策方法
- 年1回以上は単価データベースを更新(積算ソフト or 資料)
- 「材料+手間+附属部品」のセットで拾うクセをつける
- 使用頻度の高い器具・配線は「テンプレート単価」を作成しておく
- “1本いくら”ではなく“1回路ごと”の手間単価を検討する
ミスあるある③:仕様の読み違い
💬 よくあるケース
- LEDダウンライトと思っていたら、実は調光対応品だった
- 分電盤が屋内用と勘違いして拾っていた
- 100Vと200Vの混在を見落として、回路数やケーブル仕様を間違える
✅ 対策方法
- 器具リストは必ず「品番レベル」で確認(できれば型番調査も)
- 「仕様変更がないか」設計変更図・指示メールを積算前に確認
- 高圧/低圧、屋外/屋内などの仕様区分を色分けで整理する
ミスあるある④:過剰積算・不要部材の計上
💬 よくあるケース
- 工事範囲外の回路や、将来予備回路まで拾ってしまう
- 実際は使用しないBOXや配管部材を加えてしまう
✅ 対策方法
- 「施工範囲」を積算前に明確にする(赤枠で囲う・表に書く)
- 規模の大きい案件は実行積算と見積積算を分けて考える
- 経験の浅い人が積算する場合は、ベテランによる妥当性チェックを入れる
ミスあるある⑤:数量の単位ミス・換算ミス
💬 よくあるケース
- m(メートル)と本(ほん)を混同して単価を掛ける
- 1回路分の拾いで、2回路分の単価を使ってしまう
- 単価は10m単位、なのに1mで積算してしまった
✅ 対策方法
- 拾いと単価の単位は、必ず一致しているか確認
- 数量×単価を計算する前に、「換算が必要か?」を確認
- 積算書に単位欄を明記し、再チェックの時に見やすくする
まとめ:電気積算は「正確な拾い」と「ルールの徹底」が命!
積算ミスは小さなズレでも、工事全体では数万円〜数十万円の差になってしまいます。
だからこそ、“再確認の仕組み”と“拾いの手順”を整えることが、ミスを防ぐ一番の近道です。
✅ 今すぐできるミス防止アクション
- ☑ 積算時は「器具リスト ⇔ 図面 ⇔ 拾い表」の突合せを習慣に
- ☑ 単価・仕様・工事範囲のチェックリストを導入
- ☑ 担当者ごとに「拾いルール」を明文化する
- ☑ 完成前に“第三者チェック”の体制をつくる